航空大学校の受験は倍率10倍以上と厳しい道です
全員で合格なんて夢みたいな話・・・
受験なんだから、人の上に立ってこそ合格できるんじゃないの?
でも、そんな中で入試の最中、私が強く感じたのは、
「パイロットになるためには、競争よりも“協力”が大事」
ということでした。
今回は、私の受験エピソードをお話しします
✨ 2次試験の帰り道に「声をかけた」あの瞬間
私は航空大学校の2次試験Bが終わった帰り際に、
同じように試験を終えた受験者にこう声をかけました

3次試験に向けて、みんなで一緒に対策しませんか?
この様に声を掛けたのは、初回受験の時の苦い記憶があったからです。。。
初回受験の時のエピソードです
右も左もわからないまま、臨んだ3次試験
待合室は静かな場面が多く、情報共有は少ない環境でした
私も含めて同日受験者の半分程度が3次試験にて不合格
振り返ってみると、受験者同士の情報共有の少なさは顕著でした
(他の学校の入試であれば当たり前ではあるが、)
そんな記憶もあり、初対面ばかりで緊張感もありましたが、
思い切って声を掛けてみました
ひとり、またひとりと賛同してくれて、最終的に 6人の“3次試験仲間 が誕生しました
想定質問の作成、模擬面接の練習の進行など、私が中心となって勉強会をオンラインで実施
回数を重ねるごとに、互いの弱点を補い、強みを伸ばす関係性が自然にできていきました
6人中4人が初回受験でしたが、私の初回受験の時の経験も共有することで、
全員が本番をイメージできる状態になっていました
㊗️みんなで掴んだ“全員合格”という結果
私たちの目標はひとつ「全員で合格すること」
誰かを蹴落とす必要もない
ただ、お互いの成功を心から応援し合える空気が、そこには確かにありました
この空気感を作れたと確信した瞬間は嬉しかった
そして迎えた3次試験――
共に対策をした6人が最終合格
3次試験の合格率が約7割と言われる中でのこの結果は、“奇跡”のようですが、
私は違うと思っています
これは、「仲間と支え合うことの力」が正当に評価された結果だったと確信しています
✈ 3次試験当日に感じた、航大らしい空気
先述したように私自身、3次試験は2度目の受験でした
その分、他の受験生よりも知識も経験もある状態ではありましたが、
それ以上に印象的だったのが“当日の受験生たちの姿勢”でした
面接の内容や雰囲気など、試験を終えた人が、
これから受ける人へ自然と情報を共有する文化がありました
「この質問はこう聞かれたよ」「あの面接官はこういう雰囲気だった」
そんなやりとりが、暗黙の了解で、まるで当たり前のように行われていました
「誰か1人が受かればいい」のではなく、**「皆で合格しよう」**という雰囲気。
それに私は深く感動しました
パイロットという職業の本質が、
試験の場からもう始まっていたような気がしたのです
🍶 試験前夜と当日の“仲間との時間”
3次試験前日の夜、僕たち6人は“決起会”と称して軽く集まりました
オンラインのやりとりだけだった仲間と、ようやくリアルに初めて顔を合わせる瞬間でした
「明日、全員で合格しよう」
それぞれが握手を交わし、エールを送り合ったあの夜の空気は、今でも忘れられません
試験当日も、会場まで6人でタクシーを乗り合い、共に向かいました
試験が終わった後は、宮崎空港でそのまま打ち上げ(笑)
空港ラウンジで、互いの健闘を称え、これからの夢を語り合ったその時間も、大切な思い出です
そんな仲間とまた航大で再会できた時は、何物にも代えがたい感動がありました。。。
✨ “受験は孤独じゃない”と気づかせてくれた体験
この経験を通して、私は確信しました
航空大学校の受験は、競争じゃなく“協力”で戦うべきだ
そして、パイロットに必要なのは、知識や技術以前に、
「誰かと力を合わせる能力」なのだと
👍 今年、あなたも“チームで合格”を目指しませんか?
今回の記事では、「仲間、協力、感動 友情、努力、勝利」というワードを連発し、
読み返してみると、くさい記事となってしまいました笑
ですが実際の所、私はこの体験をきっかけに、
今では航大の訓練でも本気で同期と協力し合い全員で卒業したいと考えることができるようになりました
恐らく、初回受験の時に一人で対策して合格していたら、航大生活でも助け合う意識というのは少なかったのかと思います
入試を目指している後輩も同様です
パイロットになりたいという同じ志を持つ人が協力し合えるコミュニティを
1次試験の時から作れれば最高だなと考えています
- オンラインで面接練習や勉強会ができる
- モチベが下がった時に相談できる仲間がいる
- 分からないことは持ち寄って一緒に解決できる
そんな場を目指して、コミュニティ作成を検討中です
「誰かと一緒に頑張りたい」
「1人じゃ不安だけど、仲間がいれば頑張れる」
そう思った人は、今後ブログやSNSからコミュニティに関する情報を発信するのでぜひチェックしてください!
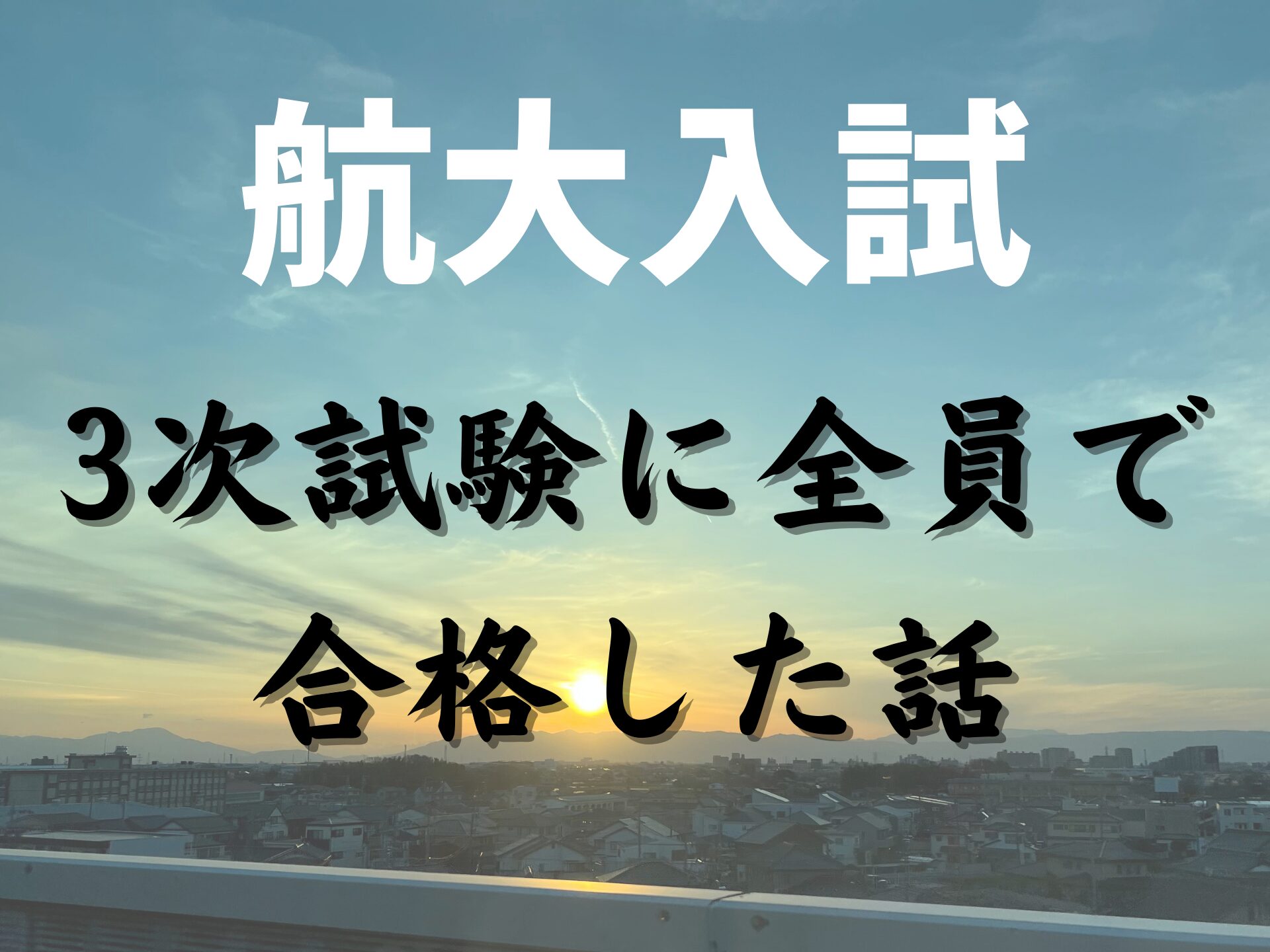


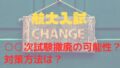
コメント